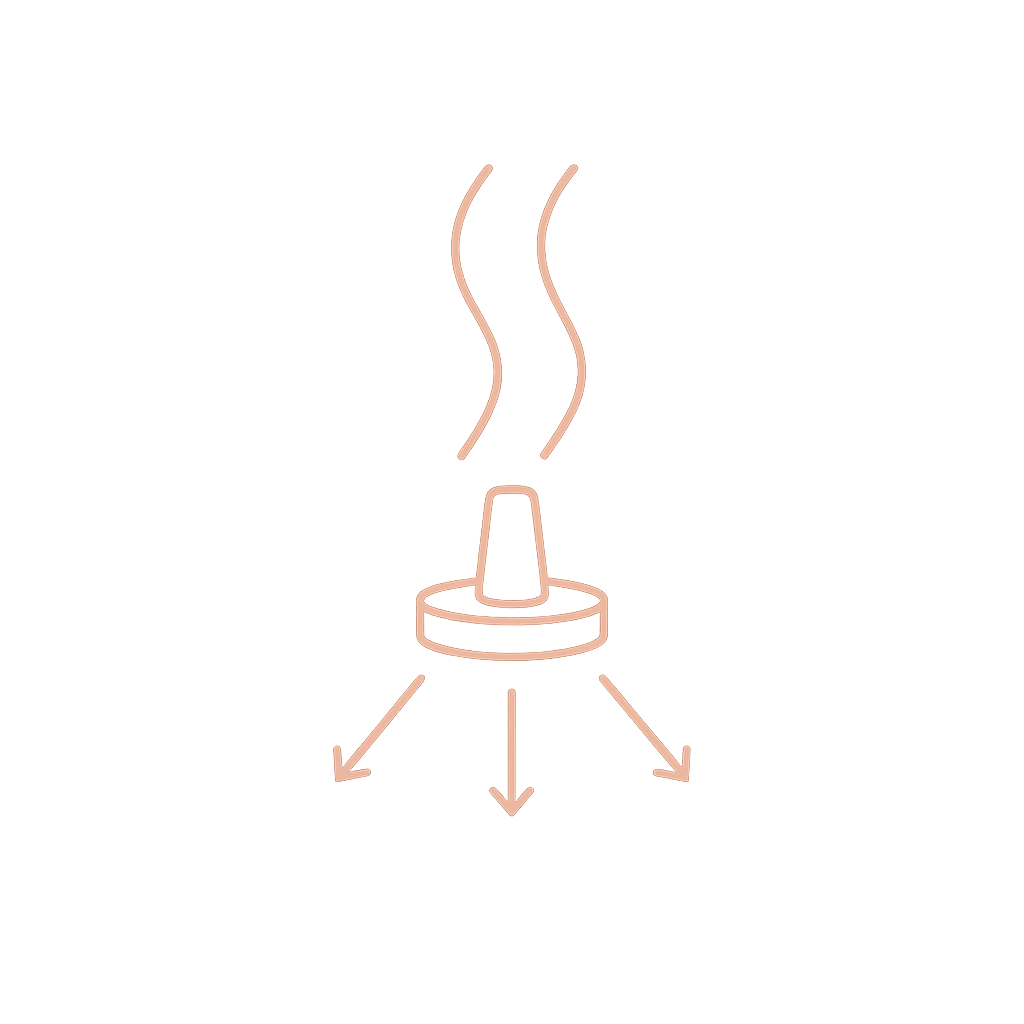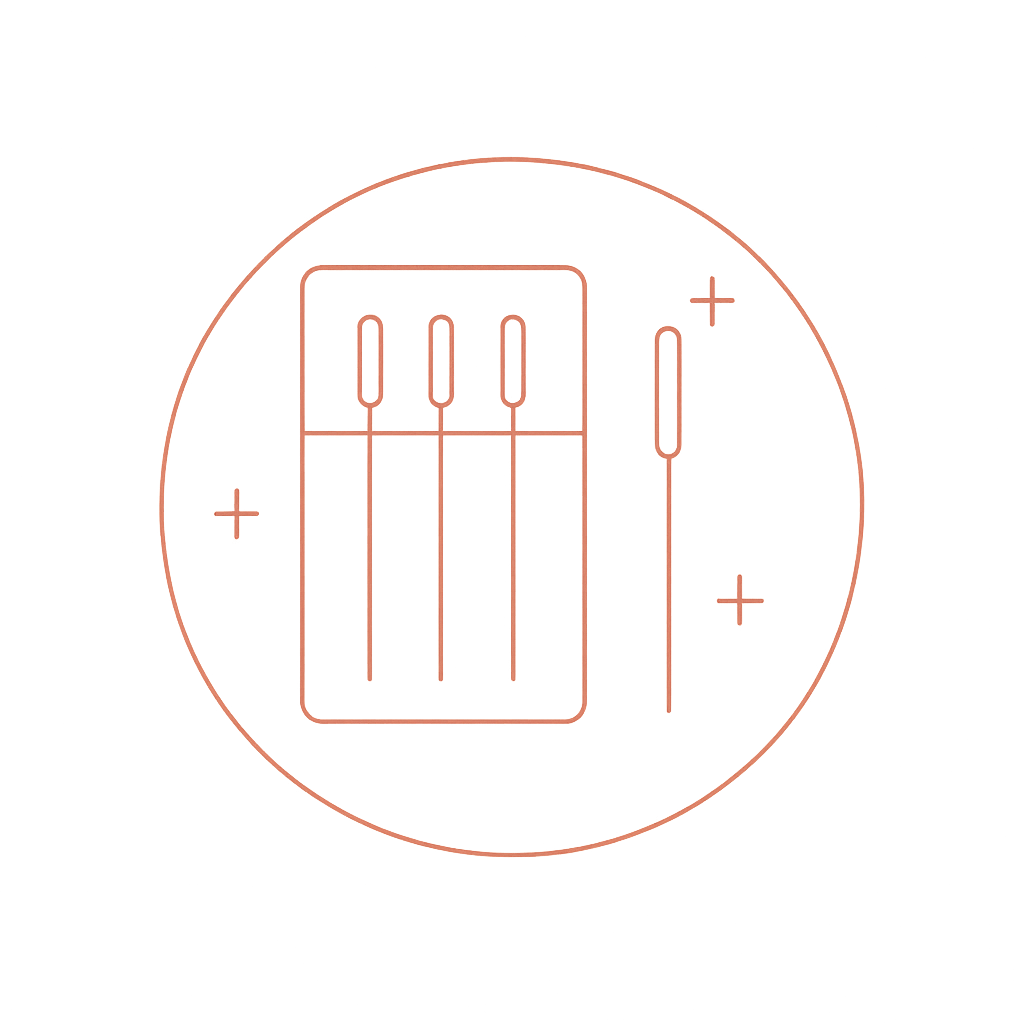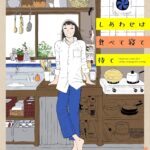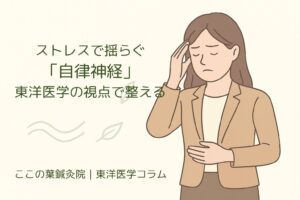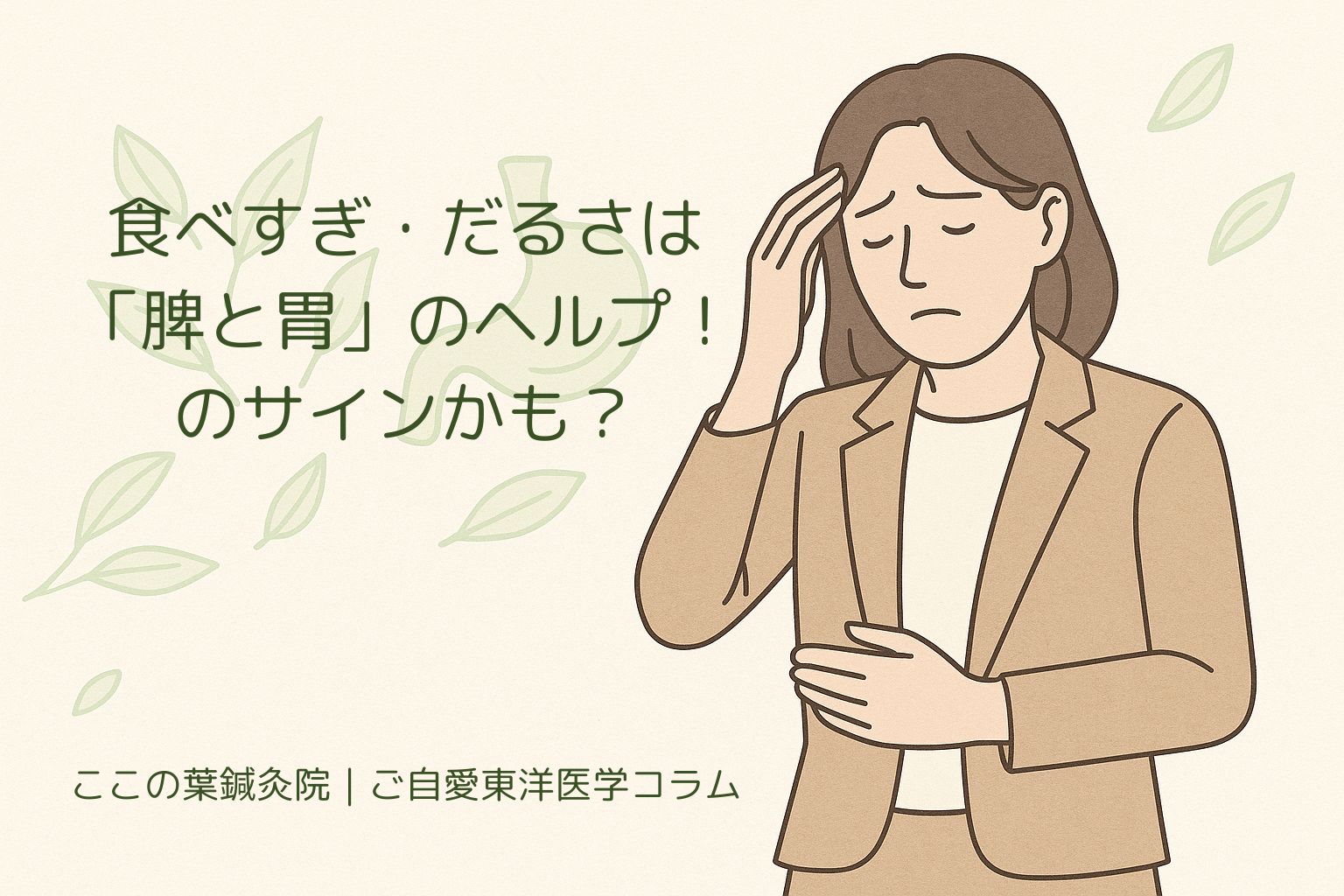
―梅雨どきにも多い“消化器の疲れ”―
こんにちは。ここの葉鍼灸院です。
このコラムでは、東洋医学の視点から、体と心を整えるヒントをお届けしています。
今回は、日々の食事や季節の変化に影響を受けやすい「脾(ひ)と胃(い)」のお話です。
◯ 脾と胃は、消化と吸収の要
東洋医学でいう「脾と胃」は、食べたものを「気(エネルギー)」や「血(けつ)」に変える、大切な器官。
現代医学での胃腸にあたる働きに加えて、私たちの“元気の源”をつくる役目があります。
脾は「運化(うんか)」、つまり食べたものを吸収し全身に届けるはたらき。
胃は「受納(じゅのう)」や「腐熟(ふじゅく)」と呼ばれる、“食べたものを受け入れ、分解していく”はたらきを持ちます。
◯ 脾と胃が疲れると、どんな症状が?
-
食欲がない/胃もたれ
-
だるい、眠い、やる気が出ない
-
下痢や軟便が続く
-
口の中がネバネバする
-
顔色が黄色っぽく、むくみやすい
これらは、脾と胃が弱っているサインかもしれません。特に梅雨の時期は「湿(しつ)」の影響で、脾胃のはたらきが低下しやすくなります。
◯ 東洋医学で見る「脾胃の不調」の種類
-
脾気虚(ひききょ):元気が出ない、食欲不振、手足のだるさ
-
脾陽虚(ひようきょ):冷え・下痢・消化力の低下
-
脾胃湿熱(ひいしつねつ):お腹の張り、口の粘り、不快感やだるさ
脾は“湿を嫌う”臓器。雨の多い時期、冷たいものの摂りすぎ、甘いものの過食なども、脾胃の働きを妨げる要因になります。
◯ 鍼灸でできるケアとセルフ養生法
当院では、こんなケアを行っています。
-
お腹への鍼灸施術:気の巡りを整え、消化器を元気に
-
お灸で脾を温める:冷えやだるさにアプローチ
-
整体で全身のめぐりをサポート
ご自宅でのセルフケアには…
-
常温以上の食べ物・飲み物を心がける
-
食べすぎ、飲みすぎを控える
-
「足三里(あしさんり)」へのお灸や指圧もおすすめです
◯ まとめ|元気の源は、胃腸から
「疲れやすい」「気分が乗らない」…
それ、実は“食べる力”=「脾と胃」が弱っているサインかもしれません。
食べたものから気や血が生まれ、体と心をめぐっているのが東洋医学の考え。
胃腸を整えることは、全身のエネルギーを整えることにつながります。
梅雨どきや夏のはじまりに、ぜひ一度、自分の脾胃の声に耳をすませてみてくださいね。